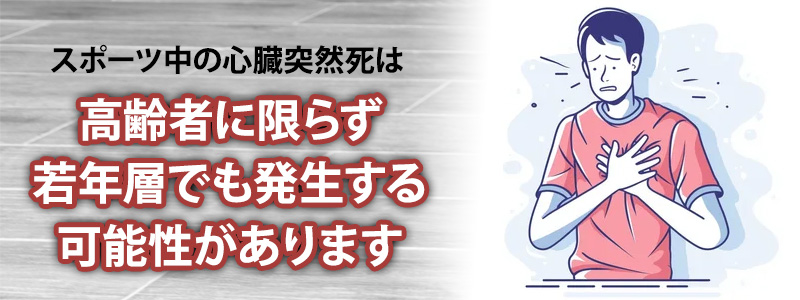スポーツ活動中に発生する心臓突然死は、決してめずらしい出来事ではありません。スポーツ選手に限らず、健康に見える若年層や運動習慣のある中高年でも発生する恐れがあります。そのため、スポーツの現場では「もしもの事態」に備える必要性が高まっています。
当記事では、スポーツ中の心臓突然死が起こる原因や発生しやすい競技、予防のための具体的な方法、実際の救命事例について解説します。スポーツ関係者や愛好者の方の、より良いスポーツ環境づくりのためにぜひご一読ください。
1. スポーツ中の心臓突然死の原因とは
スポーツ中の心臓突然死は、高齢者に限らず若年層でも発生する可能性があります。ここでは、年代に分けてスポーツ中に心臓突然死が起こる主な原因を解説します。
1-1. 高齢者の心臓突然死の主な原因
高齢者のスポーツ中の心臓突然死の主な原因疾患としては、冠動脈疾患や急性心筋梗塞、重篤な心室性不整脈、脳卒中などが挙げられます。これらの疾患は運動による急激なストレスで誘発されることがあり、運動直後の心拍・血圧の急な変化によっても心筋虚血や致死的不整脈が起こるリスクがあります。
特に、冠動脈疾患は高齢の運動愛好者における一般的な原因とされており、胸が締め付けられるような痛みが典型的な症状です。ただし、糖尿病のある人では、息切れやめまいなどの非典型的な症状しか出ないこともあります。また、肥満・糖尿病・インスリン抵抗性などを有する人は、自律神経のバランスが崩れやすく、運動中に血圧が過度に上昇したり、心電図異常が現れたりする危険性も高まります。暑い夏の時期には、熱中症で心臓突然死が起こることも考えられます。
1-2. 若年層の心臓突然死の主な原因
若年層では、外的衝撃による心臓しんとうなど、基礎疾患がない場合にもスポーツ中の心臓突然死が発生することがあります。野球のボールやホッケーのパックが胸に当たるなどの強い衝撃によって、心臓に病気がなくても不整脈が生じ、突然死に至る恐れがあります。
一方で、心筋の異常な肥厚(肥大型心筋症)のように、心臓の構造異常が原因となるケースも少なくありません。QT延長症候群やブルガダ症候群など、不整脈を引き起こす先天性の心疾患もスポーツ中の心臓突然死の一因になり得ます。拡張型心筋症のような心拡大が無症状で潜んでいるケース、ウイルス感染で心筋炎が起こるケースにも注意が必要です。マルファン症候群などの遺伝性疾患が背景にある場合は、大動脈解離や大動脈瘤が突然破裂し、致命傷になることもあります。日本ではランニング中の事例が多いと言われており、夏場は熱中症による突然死リスクが上がります。
2. 突然死がよく起こっているスポーツ種目
スポーツ中の心臓突然死は、種目や年齢層によって発生頻度や発生率、危険率が異なります。60歳以上ではゲートボールやゴルフ、登山などが注意を要する種目です。40~59歳ではゴルフやランニング、水泳などで突然死が発生しています。
若年層では球技関連における突然死の発生が多くなっています。サッカーのように運動強度や運動負荷が高い種目は、心臓への負荷が大きいため、突然死のリスクが高いとされています。また、硬式野球やホッケーなどの競技では、胸部への強い衝撃による心臓しんとうが原因となるケースもあります。
スポーツ中の心臓突然死は決してめずらしい現象ではなく、いつ・どこで起きるか予測できません。万が一に備えて、スポーツ現場にはAED(自動体外式除細動器)を常備し、迅速に使用できる体制を整えることが、命を救う有力な手段となるでしょう。
3. スポーツ中の心臓突然死を防ぐ方法
スポーツ中の心臓突然死は予測が難しいものの、適切な備えと対策により心肺停止のリスクを減らすことはできます。ここでは、スポーツ中の心臓突然死の予防方法と緊急対応について解説します。
3-1. AEDを準備する
心停止の際に有効な救命措置の1つが、AEDによる電気ショックです。AEDは、致死性不整脈の1つである心室細動を検出し、電気ショックによって心拍を正常に戻す装置です。「令和6年版 救急救助の現況」によると、救急車到着前にAEDを使用した場合、1か月後の生存率は約54.2%、社会復帰率は約44.9%であり、未使用時と比べて蘇生率が向上することは明らかです。
スポーツ現場は心臓突然死が発生しやすく、かつ目撃者や救助者が多い環境であるため、AEDを適切に設置・運用する必要があります。競技場や体育館、プール、公園、学校などには、目立つ場所にAEDを複数配置し、およそ2分以内に取りに行ける距離を目安に体制を整えるのが理想です。また、屋外イベントや合宿、遠征などには携行型やレンタルAEDの活用も検討されます。
3-2. スタッフが救命講習に参加する
スポーツ中の心臓突然死に対応するには、その場にいるスタッフや選手自身が迅速に行動する必要があります。実際、コーチやトレーナーなどのスポーツ関係者が救命処置に加わる場面は多く、参加者全員が救命講習を受けることが救命率向上につながるでしょう。たとえAEDを2分以内に持ち込める環境が整っていても、使用判断が遅れれば、救命の可能性は下がります。
また、仰向け以外で倒れているケースや、防具を装着した選手に対するケースも想定し、訓練を通して救命体制を整えることも重要です。AEDは音声ガイドに従って使用できる設計ですが、一度救命講習を受けることで、落ち着いて迅速に操作できるようになるでしょう。
3-3. エマージェンシー・アクション・プラン(EAP)を準備する
エマージェンシー・アクション・プラン(EAP)は「緊急時対応計画」とも呼ばれ、スポーツ中の事故や心停止といった緊急事態の際、迅速かつ適切な救急対応を行うために事前に作成する計画のことです。EAPは、医療関係者が常駐していない場面でも対応できる体制を整えることを目的としており、救護体制の明確化と迅速な対応を可能にします。
EAPを作成するときは、「起こり得るけがや病気の種類」「救急資機材の準備(AED・救急箱など)」「処置方法」「AEDの設置場所」「救急車の進入経路」「近隣病院の情報」などの情報を含めます。大会や大規模施設ではEAPを作成・掲示するほか、部活動や日常の練習・トレーニング現場でも作成と携行が求められます。
3-4. メディカルチェックを事前に行う
メディカルチェックは、スポーツに参加する前に心臓突然死を含む健康リスクがないかを確認する健康診断です。特に中高年では、高血圧・脂質異常・糖尿病などの生活習慣病が狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患につながる場合があるため、自覚症状がなくても潜在的な疾患を早期に見つけることは重要です。若年者においても、心臓に構造的な異常がなくても運動によって不整脈が誘発されてスポーツ時の死亡リスクにつながる恐れがあるため、不整脈の有無や誘発の可能性をチェックしましょう。
ただし、メディカルチェックだけでリスクを完全に排除できるわけではありません。スポーツ当日は、発熱・だるさ・下痢・睡眠不足・関節の痛み・過労の有無などを確認するセルフチェックも行い、体調に異変がある場合は無理に参加しない判断が求められるでしょう。
4. スポーツ中の心臓突然死を防げた事例・防げなかった事例
スポーツ中の心臓突然死は、適切なAED使用があれば防げるケースも多く存在します。ここでは、実際の現場で起こったスポーツ事故を通じて、救命に成功した事例と、対応が遅れたことで尊い命を救えなかった事例を紹介します。
- 防げた事例
高校野球の試合中、投手として出場していた選手が打球を胸に受けて意識を失い、心停止状態に陥りました。監督による胸骨圧迫、保護者による人工呼吸、そして現場にいた救急救命士が学校に設置されていたAEDを使用して処置を行いました。その結果、救急車で搬送される途中に呼吸が戻り、後遺症もなく短期間で復帰できました。 - 防げなかった事例
2024年、インドネシアで開催されたバドミントンのアジアジュニア選手権中に、中国の17歳の選手が試合中に突然倒れました。心肺蘇生もAED使用もされないまま搬送され、心不全により死亡が確認されました。競技中の緊急時対応の重要性と、その場にいる全員の迅速な判断と行動の必要性が問われる事例です。
上記の事例から分かるのは、ただAEDを設置すればよいだけでなく、「誰が・どのように・どのタイミングで使うのか」という体制づくりが非常に重要である点です。日常的な訓練と備えが、かけがえのない命を守る力となるでしょう。
その備えを実践的に身につけられるのが、フクダ電子のAED講習会「F'session」です。胸骨圧迫とAEDの使用方法を中心に学べ、希望者の方は小児(未就学児)救命や人工呼吸も体験できます。いざというときに確かな行動につなげるために、ぜひ受講をご検討ください。
まとめ
スポーツ中の心臓突然死は、高齢者だけでなく若年層にも起こり得る深刻なリスクです。主な原因には、加齢に伴う冠動脈疾患や心室性不整脈、若年者における先天性心疾患や心臓しんとうなどがあり、競技種目や運動の強度によって発生リスクも異なります。
スポーツ中の心臓突然死のリスクを軽減するためには、AEDの設置と活用体制の整備、スタッフや選手への救命講習の受講、EAPの作成、事前のメディカルチェックといった多角的な対策が欠かせません。実際に、AED設置と迅速な対応によって救命に成功した事例も存在します。
AEDの販売やレンタルサービスを提供するフクダ電子は、千葉ロッテマリーンズや東北楽天ゴールデンイーグルス、公益社団法人 日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)のスポンサーとして、スポーツの安全と振興に貢献しています。AEDに関する詳細はフクダ電子のAED製品情報ページをご覧ください。